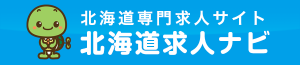第143回「三笠市の寮裏にできた「みんなの畑」プロジェクト」
こんにちは、北海道ハピネス株式会社の高橋です。
今回は、私が担当した「寮の裏庭に作った畑」についてご紹介したいと思います。
当社は登録支援機関として、三笠市の食品工場に3名のベトナム人女性を紹介し、現在日々の生活や仕事のサポートを行っています。
彼女たちは年齢も性格も異なり、もともとは全くの他人同士。最初は引っ越しのタイミングもバラバラで、生活を共にする中でどうしても見えない壁ができてしまい、時には本当に深刻なトラブルもありました。
【みんなで一つの目標を――「畑プロジェクト」の始動】
そんな中、「みんなで一つのことを目標にして楽しめる何かを作りたい」と考え、以前から皆が「もしあれば嬉しい」と話していた畑作りに挑戦しました。
最初は荒れた土地の寸法を測り、草と石を処理。大枠をスコップで耕すところからスタート。週末に一気に作業を進め、そこから少しずつ仕事の合間に寄って少しずつ土を起こし、レンガで枠を作り、畑の大枠を完成させました。作業は大変でしたが、「これがきっとみんなの新しい居場所になる」と思うと、不思議と力が湧いてきました。

草と石の処理*汗だくです(笑)
土を耕し始めた様子とレンガで枠を作成した様子
種や苗を植えている様子
【みんなの笑顔が生まれた瞬間】
ある日、畑の様子を見に行くと、3人がすでに種や苗を植え始めていました。畑は一気に“みんなの畑”へと変身し、彼女たちの嬉しそうな笑顔がとても印象的でした。
今では毎日水やりをし、週末には3人で畑仕事を楽しんでいるようです。一つの畑を通じて自然と会話が増え、協力し合う姿が見られるようになりました。以前私が感じていた壁も、今ではそれが嘘だったかのように、とても仲良しで協力し合っているように感じます☆
「畑の大枠」と「絆の大枠」――登録支援機関としてのやりがい
今回、私が作った畑の大枠は、まさに三人の新しい生活の「舞台」を用意するようなものでした。レンガで囲い、土を整えたその枠は、これから始まる彼女たちの共同生活の“土台”でもあります。
その畑に命を吹き込み育てているのは、一つ屋根の下に暮らす3人の彼女達です。農作物を大切に少しずつ育てるように、それは同時に少しずつ自分たちの居場所を作り上げていっていると思います。
私は形として「畑の大枠」を用意しただけですが、彼女たちがその中で共同で土を耕し、種をまき、苗を植え、日々手をかけて育てていっている姿を見ていると、それは正に「3人の絆の大枠」を一緒に作っているような気持ちになりました。
1名恥ずかしがって写らなかったですが、皆凄く喜んでいます(笑)
畑の大枠は、三人の絆の大枠
彼女たちが今少しずつ育てているのは、野菜だけでなく、互いへの信頼や思いやり、そして新しい日本での生活そのものです。
登録支援機関としてのやりがいは、こうした「目に見えるサポート」だけでなく、母国から離れてそれぞれに色んな思いを背負って日本に来てくれている彼女たちが安心して暮らし、少しずつ心を通わせていく“土台”や“きっかけ”を作れることにあると私自身強く感じます。
彼女たちの考え方や行動を見て感じたのは、人は結局、国籍なんて関係なく、愛情を与えられるかどうか、思いやりを受け取れるかどうかが、結局はその人の心の成長として育っていくものだと思うのです。
畑の土に水をやり、太陽の光を浴びて芽が伸びていくように、人の心もまた、優しさや信頼という“目に見えない栄養”を受けて、静かに、でも確かに成長していくのだと。
国が違っても、言葉が違っても、心が通い合う瞬間の温かさは、誰にとっても同じです。人は「外国人」や「日本人」といったラベルではなく、みな同じ“人”として愛し、悩み、支え合って生きている。そう改めて実感しました。
まだまだ海外事業は始まったばかりです。私は世に当たり前にある形だけの登録支援機関としての仕事ではなく、北海道ハピネス株式会社の強みである「人に優しい」登録支援機関としての有り方をこれからも模索し、国籍を超えて支え合いながら共に歩んでいける社会を目指していきたいと思っています。
今回、畑の成長とともに三人の絆がさらに深まっていくことを願いながら、私自身も本当の意味での支援者として歩んでいきたいと考えています。
次は帯広事業所の木村主任です☆